幼児期の子供をお持ちの親御さんは、「元気に育ってくれればそれでいい!」と思いつつも、お子さんの「頭の良さ」について少なからず気になるのではないでしょうか。
今の世の中いろいろな生き方があるけれど、何をするにもやはり『地頭』が良いに越したことはないですよね。
ここでは、現役東大生や卒業生、その親に向けた6つのアンケートの内容を総まとめし、頭の良い人たちがどんな幼児期を過ごしていたのかを探っていきます。
必ずしも難関校に入ることだけが良いわけではないけれど、東大の入試問題は知識偏重型ではなく高い思考力や表現力を問うもの。
東大に合格した人の幼少期の過ごし方は、参考になるヒントがたくさん詰まっていますよ。
モンテッソーリ教育とチャイルドコーチングの指導者で、1児の母でもある筆者が、詳しく解説していきます。
使用した東大生アンケート
■公文『大学生意識調査ー東京大学編』現役東大生100人 (2015年)
■東大卒ママの会『東大及び院生が受けた幼少期の教育アンケート
■レゴジャパン『レゴと知育の関連性に関する調査』東大卒100人(2018年)
■株式会社コペル『幼少期の教育環境に関する調査』東大卒518人/東大以外卒604人 (2020年12月)
■株式会社インタースペース『東大生は幼少期どのような生活を送っていたのか』現役東大生302人 (2021年5月)
★東大生の小学生時代の過ごし方はこちらからどうぞ 子供が小学生になると、どうしても「頭の良さ」が気になってきますよね。 一概に、「学校の成績が良い子=本当に頭がいい子」とは限らないけれど、ここでは東大生が小学生の頃どのように過ごしてきたか、親がどう接 ... 続きを見る 小学生の子を持つ親御さん、放課後の時間をどうしていますか? 習い事、ゲームやテレビとの付き合い方、家のお手伝いなど…何をどの程度させたらよいのか、迷いますよね。 ここでは、1つの例として東大生が小学生 ... 続きを見る

【東大アンケート総集】頭が良くなる小学校生活・勉強はどれくらい?

頭の良くなる小学生生活・遊びと生活編【東大アンケート総まとめ】
東大生の幼児期の生活アンケート
まずは、東大生が幼児期にどんな生活をしていたのか見ていきましょう。
東大生は幼児のとき何時に寝ていた?

最初は就寝時間の比較から。
Q. 幼児期に何時に寝ていた?
| 東大生家庭 | 幼児全般 | |
| 〜19:00 | 1.7% | 0.7% |
| 19:30頃 | 1.7% | 2.4% |
| 20:00頃 | 25.0% | 6.9% |
| 20:30頃 | 16.7% | 13.7% |
| 21:00頃 | 36.7% | 28.5% |
| 21:30頃 | 6.7% | 23.0% |
| 22:00頃 | 5.0% | 15.2% |
| 22:30〜 | 6.7% | 8.8% |
ベネッセ教育総合研究所『幼児の生活アンケート』未就学児を持つ首都圏の保護者4034名 (2015年)
東大生家庭も一般家庭も、21時頃に寝かせていたという家庭が一番多いですね。
でも、その前後が大きく違います。
一般家庭では21時を過ぎても起きている子が47%もいるのに対し、東大生家庭ではたったの18.4%。
昔から「寝る子は育つ」と言われているけれど、体の成長だけでなく脳の発達や記憶の定着のためにも、たっぷりと睡眠をとることは大切と言われています。
特に保育園に通う子は、幼稚園に通う子よりも平均で1時間くらい就寝時間が遅くなる傾向があるので、時間の使い方を上手に工夫してなるべく早く寝られるようにしたいですね。
東大生は幼児期にテレビをどれくらい見ていた?
とりあえずつけておけば、子供が静かに見てくれるテレビ。
家事をしたい時やちょっと一休みしたい時など、ついつい頼ってしまいますよね。
では東大生は、幼児期にどれくらいテレビを見ていたのでしょうか?
Q. 幼児期にテレビを1日どれくらい見ていた?
| 東大生家庭 | 一般家庭 | |
| 0分またはテレビがない | 5.0% | 2.3% |
| 30分 | 20.0% | 17.4% |
| 1時間 | 38.3% | 29.2% |
| 2時間 | 26.7% | 27.3% |
| 3時間 | 6.7% | 13.7% |
| 4時間 | 0% | 5.0% |
| 5時間 | 1.7% | 1.6% |
| 5時間30分以上 | 1.7% | 2.5% |
どちらも一番多いのは『1日1時間』。30分番組を2つ分です。
2時間以上見る家庭は、東大生家庭で36.8%・一般家庭では50.1%。
差はあるけれど、結構東大生も幼児期に結構テレビを見ていたんだなと思い、ちょっと安心しました。
ただし、たとえEテレなどの教育番組でも、どうしても一方通行になってしまうテレビやビデオでは脳が活発に働かないことがわかっています。
テレビばかりではなく、自分で考えたり工夫したりできる遊びの時間を多くすることが頭を良くするにはおすすめですよ。
★こちらの記事も読まれています 「これからは思考力が大切!」と言われる昨今。 そう言われても、子供をどう育てればよいのか迷っている親御さんも多いと思いのではないでしょうか? 私たち親世代が子供の頃は、計算や暗記がいかに得意かで出来不 ... 続きを見る

子供の思考力を鍛える3つのステップ
東大生は幼児期に本の読み聞かせをどれくらいしていた?

次に『本の読み聞かせ』。
これは東大生家庭と一般家庭でかなりの違いがありました。
Q. 幼児期に本の読み聞かせをどれくらいしていた?
| 東大生家庭 | 一般家庭 | |
| ほとんど毎日 | 68.3% | 25.5% |
| 週に3~4日 | 16.7% | 17.8% |
| 週に1~2日 | 11.7% | 30.0% |
| ごくたまに | 1.7% | 15.5% |
| 読み聞かせはしない | 1.7% | 10.0% |
ベネッセ教育総合研究所『幼児期から小学1年生の家庭教育調査・縦断調査3〜5歳児約1000人』年中時の読み聞かせ(2014年)
週に3日以上本の読み聞かせをしていた家庭は、東大生家庭で85%にも上り、一般家庭の43.3%のおよそ倍!
また回数だけではなく、1回に読む本の冊数も大きく異なります。
学研教育総合研究所の『幼児白書Web版』(2019年8月)によると、一般的な幼児の読書量(自読・読み聞かせを含む)は1か月で平均4.2冊。
それに比べ、東大生家庭では幼児期の1回の読み聞かせの冊数が平均3.5冊。
毎日読むとすると、1か月で100冊を超える量になります。
読み聞かせを始めた時期は、東大生家庭のおよそ35%が生後3カ月未満から行っていたそうですよ。
読み聞かせのメリットは、語彙力や読解力など国語に直結する力が付くだけではなく、集中力や想像力も養えること。
また、親が自分の一番近くで自分の為に時間を割いてくれることで愛情をたっぷり感じ、自己肯定感も高まると言われています。
事実、現役東大生100人に調査した『公文の大学生意識調査ー東京大学編』(2015年)では、「子供のころ親にしてもらって感謝している教育とは?」という質問に、100人中40人の東大生が「本の読み聞かせ」と答えていました。
まさに、読み聞かせは親子の最高のコミュニケーションと言えるでしょう。
読み聞かせる本の内容については、富永雄輔さんの著書『東大生を育てる親は家の中で何をしているのか?』(文響社)では、「子供が好きな本、子供が自分で選んだ本を読むことが大切」と書かれています。
また、東大卒ママの会では、動植物などの自然の本、からだに関する本、季節を感じられる本がおすすめされています。
そして読み聞かせには向かないかもしれないけれど、『図鑑』もまた多くの東大生が幼児期から身近にあったと言われるものの一つ。
東大卒ママの会が東大および東大大学院の現役学生・卒業生257人を対象にした『東大及び院生が受けた幼少期の教育アンケート』では、
リビングに置いてあって役立ったもの
1位 絵本・本(62%)
2位 図鑑(49%)
3位 地図(42%)
(複数回答可)
となっています。
早いうちからリビングに図鑑や地図を置いておいて、わからないことがあったらすぐに親子で一緒に調べる習慣をつけておけば、「知りたい!」という知識欲や探求心が養えますよ。
ちなみに、本をたくさん読むご家庭では図書館を利用することが多いそうです。
たいていの図書館では1度に10冊以上借りることができるので、上手に活用していきたいですね。
東大生は幼児期に何で遊んでいた?

また、読み聞かせの他にも頭の良い子になると言われている遊びがあります。
それは『積み木やブロック遊び』。
将棋の藤井聡太さんが幼児期に遊んでいたという立体パズル『キュボロ』が、一時期話題になりましたね。
東大生もやはり幼少期に積み木やブロック遊びを多くしていたのでしょうか?
Q. 幼児期に積み木・ブロックなどの知育グッズでの遊びをどれくらいしていた?
| 東大生家庭 | 一般家庭 | |
| ほとんど毎日 | 51.7% | 29.9% |
| 週に3~4日 | 33.3% | 22.8% |
| 週に1~2日 | 8.3% | 20.5% |
| ごくたまに | 6.7% | 24.1% |
| 使わなかった | 0% | 1.2% |
| 家になかった | 0% | 1.3% |
ベネッセ教育総合研究所『幼児の生活アンケート』未就学児を持つ首都圏の保護者4034名 (2015年)
これもかなり差がありますね。週に3日以上積み木やブロックなどの知育グッズで遊んでいた子は、東大生家庭で85%、一般家庭で52.7%。
玩具メーカーのレゴジャパンが2018年に行った『レゴと知育の関連性に関する調査』でも、「レゴブロックで遊んだことがあるか?」という問いに、東大出身者100人のうち68%が「ある」と回答しました。
またそのうち「子どもの頃にレゴで遊んだという経験が、自身の能力やセンスに影響があったか?」という質問に対し、85%が「影響があった」と答えています。
積み木やブロック遊びで身につく力は、想像力・創造力・空間認識力・思考力・表現力・集中力など。
また、手先を使うことで脳への直接的な刺激も高まります。
特に、説明書通りに組み立てるよりも自由に組み立てるほうがより創造力や表現力を鍛えられますよ。
先のレゴジャパンの東大出身者へのアンケート(複数回答可)でも、「説明書付のレゴを好んでいた」が22%なのに対し、「説明書無しで自由に組み立てるタイプのレゴを好んでいた」は94%と、圧倒的でした。
脳を鍛えられるブロック玩具には、『レゴ』や『キュボロ
』の他にも、『ピタゴラス
』『公文・くみくみスロープ
』『ボーネルンド・マグフォーマー
』『東京書籍・ポリドロン
』『ラキュー
』等があります。
最近出たものでは、『バンダイ・ころがスイッチ』もプログラミング力も養える玩具として人気が高いですね。
また、東大卒ママの会の著書『「東大脳」を育てる3歳までの習慣』(小学館)では、『迷路』や『パズル』も東大生が幼児期によくしていた遊びとしてあげられています。
東大生が幼少期に夢中になった遊び
迷路 83%
パズル 64%
(複数回答可)
迷路やパズルは、集中力や根気が養え、かつ完成した時の達成感が得やすい遊び。
「自分で迷路を作っていた」という東大生も多いそうですよ。
パズルでは、国や都道府県の名前を覚えたり図形や色彩的理解が強くなったという声もあります。
さらに、幼児教室コペルを運営する株式会社コペルが2020年12月に実施した『幼少期の教育環境に関する調査』では、東大卒(518名)と東大以外卒(604名)の差が大きかったあそびとして、『計算ゲーム』と『おままごと』をあげています。
| 東大生家庭 | 一般家庭 | |
| 計算ゲーム | 13.7% | 7.0% |
| おままごと | 20.1% | 13.7% |
計算ゲームは、食事の時に「いちご6個を3人で分けたら1人何個?じゃあ2人で分けたら?」など、机上のドリルではなく親子の日常会話の中で計算力をつけるもの。
そして意外だと思われるおままごとも、子供にとっては頭と心をフル回転させる遊びです。
ストーリーや台詞を考えるのに頭を使うだけでなく、登場人物の気持ちも考えるので情緒も育ちますよ。
また、天体観測やコンサートで生演奏を聴くなど、『本物』に触れさせる機会も東大生家庭では意識して多く持っていたそうです。
ここまであげられた『積み木・ブロック・パズル・迷路・計算ゲーム・おままごと・天体観測・コンサート鑑賞』は、お気付きかもしれませんがすべて基本的に大人と一緒にすること。
正直言って頻繁に付き合うのは大変なこともありますよね(笑)
テレビをぽちっとつけて見せておくほうがずっと楽です^^;
でも、こうして東大アンケートを調べれば調べるほど、「頭がよくなるには、本人の才能や努力だけではなく、親の努力や根気も大きい」ということが、本当によくわかります。
★こちらの記事も読まれています いま世界中で注目されている最新の教育、『STEAM(スティーム)教育』。 日本では文部科学省が、小学校からSTEAM教育の一部であるプログラミング学習を導入しているけれど、幼稚園・保育園でのSTEAM ... 続きを見る

幼児のSTEAM教育のメリットや弊害は?おすすめ通信教材
東大生は幼児期に親とたくさん話していた?
東大生が小さい頃に親が付き合ったのは、遊びだけではありません。
東大卒ママの会が東大及び東大大学院の現役・卒業生257人に「小さいころから親とよく会話をしていたか?」と聞いたところ、80%以上が Yes と答えたそう。
東大卒の子供を持つママたちは、
- 「ワンワン」「ブーブー」などの赤ちゃん言葉を使わない。
- 「車だね」ではなく「赤い車だね」など、形容詞をつける。
- 「ご飯食べようね」ではなく「ご飯を食べようね」など、助詞をしっかりつける。
- ちょっとしたことでも、「今日の〇〇はどうする?」と子供の意見を聞く。
- なぞなぞやしりとりなどの言葉遊びを日常的に行う。
などを心掛けたそうですよ。
また、2021年5月に株式会社インタースペースが現役東大生302人に行った『東大生は幼少期どのような生活を送っていたのか』の実態調査でも、9割以上の学生が「幼少期に親はよく話を聞いてくれた」と回答しています。
「ケータイやPCをいじらず、目を見て話を聞いてくれた。」
「自分の疑問になるべく答えようとしてくれた。大人同士の話も、子供にわかるように噛み砕いて教えてくれた。」
という声も。
子供の語彙力は、小学校入学の時点で少ない子は3000語、多い子は10,000語とかなりの差が開くことがわかっています。
2016年9月29日のPRESIDENT Online によると、その差は主に母親との会話の量や質によるものだそう。
ボキャブラリーが多いということは、単に知識として言葉を知っているだけでなく、それらを組み合わせて使いこなすために思考力や想像力もどんどん養われていきます。
そして、親が自分の話を聞いてくれることで自己肯定感も育つという一石二鳥。
たかが会話、されど会話ですね。
頭の良い子に育てるためには、忙しい毎日の中でも子供と会話する時間を大切にするようにしたほうが良さそうです。
東大生の幼児期のお勉強と習い事アンケート
さて、ここまでは東大生の幼児期の日常生活についてのアンケート結果の中から、頭の良い子に育つ秘訣を探ってきました。
次に、東大生の幼児期のお勉強や習い事事情についてみていきましょう。
東大生は幼児期からお勉強していた?

東大に合格するということは、言わずもがな「成績が良い・お勉強ができる」ということになるけれど、果たして東大生はいつからお勉強を始めたのでしょうか?
Q. 幼児期にドリルなどのワークをどのくらいさせていた?
| 東大生家庭 | 一般家庭 | |
| ほとんど毎日 | 21.7% | 7.7% |
| 週に3~4日 | 不明 | 9.3% |
| 週に1~2日 | 不明 | 17.9% |
| ごくたまに | 不明 | 32.0% |
| 使わなかった・家になかった | 23.3% | 32.5% |
ベネッセ教育総合研究所『幼児の生活アンケート』未就学児を持つ首都圏の保護者4034名 (2015年)
これを見ると、確かに一般家庭と比較すると、東大に入る子たちは幼児期からドリルをやっていた割合が高いですね。
でも、毎日やっていた子が21.7%というのは将来東大に入る子にしては少ないような気が。
そして一切やらない子も23.3%と、それ以上に多いことがわかります。
これには、東大生家庭の教育方針が、決して『ドリルでの読み書き計算の先取り学習』に偏っていないことを示しています。
ドリルをやらないからと言って何も教育をしていないかというと、決してそういうわけではないようです。
上で述べたような本の読み聞かせ、頭を使う遊び、親子の豊富な会話、本物体験などが、子供の地頭を良くして最終的に成績を伸ばしています。
東大生家庭のアンケートのコメントでも、
「無理矢理やらせて、勉強に対する苦手意識を持たせない」
「必ず親が付き添って、一緒に楽しんでやる」
「計算ドリルにこだわらず、パズル本や数独など何でも子供が好きなものをやらせる」
といった、幼児教育に対する確固たるポリシーが見えました。
高度な幼児教育というと、『小学校の勉強をどこまで先取りするか』と思いがちだけれど、いかに日常の中で頭を使っていくか、自分で考える力を身につけるかが、本当に地頭を良くするには大切なんですね。
★東大生が幼少期によくやっていたパズル本シリーズはこちら
宮本算数教室『賢くなるパズル』(Amazon)
★こちらの記事も読まれています 幼児通信教育で何を優先して身につけるべき? 幼児教育と聞くと、 「幼児から本当に勉強が必要なのかな?」 と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。 でも、子供の長い教育期間の中で一番大切にするべきなのは ... 続きを見る

幼児通信教育教材おすすめ9社比較!口コミ人気教材を解説[2024]
東大生が入学前にできるようにしたことは?

そうは言っても、「小学校入学前にある程度のお勉強はしておいたほうがいいのでは?」と思いますよね。
実際に東大生が入学前にどこまでお勉強をしていたかをみてみましょう。
Q. 小学校入学までにできるようにしていたことは?(複数回答可)
| 東大生家庭 | 一般家庭 | |
| ひらがなが読める | 86.7% | 81.3% |
| ひらがなを書ける | 83.3% | 64.0% |
| 数字を100まで数える | 71.7% | 不明 |
| 1桁の足し算 | 56.7% | 45.8% |
| 九九 | 23.3% | 不明 |
| アルファベットの読み書きができる | 18.3% | 11.3% |
学研教育総合研究所『幼児白書Web版』6歳時 (2019年8月)
ひらがなの読みは、小学校入学までに東大生家庭も一般家庭もほとんどの子がマスターしています。
一方でひらがなの書きについては20%近い差が。
ただこれに関しては賛否両論があり、手が小さく握力が弱いうちに自己流で書き癖をつけてしまうよりも、小学校に入ってから書き始めたほうが字が綺麗になるという考え方もあります。
また計算については、幼児教室のサイトなどで「九九は年長までに覚えましょう。小学校に入ってからでは遅すぎます。」といった文言を見るけれど、実際に東大生で年長までに九九を覚えていた子は23.3%。
残りの76.7%は、幼児期には九九はやっていないということです。
幼児期にたくさん先取り学習をすると、確かに小学校でのお勉強で有利になります。
でもそのアドバンテージもせいぜい2~3年生まで。
その後は、先取りしてきた子より『地頭が良い子』がグンと伸びることがわかっていますよ。
発達心理学のお茶の水女子大学内田伸子名誉教授が、2017年に2,000世帯を対象に「親は子どもが乳幼児期~児童期に何に配慮して子育てしたか」を調査した結果では、
割合が高いことがわかっています。
また、幼稚園や保育園を選ぶ基準でも、お勉強中心の園よりも「のびのび遊ばせてくれる園」を選ぶ親が東大生家庭では一番多く、上記の内田名誉教授の研究にも、
と書かれています。
幼児期にお勉強をすることが悪いわけではありません。
でも、必要最低限な文字や数を習得すれば、残りの時間は九九などの高度な先取り学習に充てるのではなく、子供が好きな遊びの中で好奇心や自発性を伸ばすことに専念したほうが、後々よさそうですね。
東大生の幼児期の習い事は?

最後は、一般的に3歳で約半数、5歳では7割以上の子供が何かしら始めているという『習い事』。
東大に合格する人は、幼児期にどんな習い事をしていたのでしょうか?
Q. 幼児期(就学前)にやらせていた習い事やお稽古事は?(複数回答可)
| 東大生家庭 | 一般家庭 | |
| スイミング | 56.7% | 35.9% |
| 楽器 | 41.7% | 12.9% |
| 英会話 | 26.7% | 30.1% |
| 塾・幼児教室 | 23% | 9.7% |
| 体操 | 21.7% | 22.0% |
| サッカー | 21.7% | 7.1% |
| リトミック | 15.0% | 10.0% |
| バレエ | 13.3% | 3.9% |
ケイコとマナブ『子どもの習い事ランキング』309名 (2017年)
東大に入る子とそうでない子で一番差が大きかったのは『楽器』で、30%近い差がありました。
楽器を習う子は幼児全体の約13%で、そのうち約8割が女の子。
東大生は8~9割が男子学生にもかかわらず、約40%が幼少期に楽器を習っていたというのは驚異的な数字です。
また、スイミング・塾や幼児教室・サッカー・リトミック・バレエも、東大生の方が多くやっていたことがわかりますね。
習い事による学力への影響は、近年脳科学でも分析され、特にピアノ・水泳・サッカーなどは発達途中の脳にとても良い影響を与えることがわかっています。
まとめ 〜頭の良い子は幼児期に何をしていた?

以上、東大生が小学校入学前の幼児期にどんなことをしていたのか、6つの東大生アンケートを総合して分析してみてきました。
ここでわかったのは、東大に入るお子さんの親御さんはしっかりとポリシーを持って賢い子育てをしているということ。
賢い子育てというのは、決して知識の詰め込み教育をしたり、小学校のお勉強をガンガン先取りさせたり、ということではありません。
子供が自ら『学ぶこと』を好きになるように上手に導く、そんな力があるように感じました。
現に東大生のアンケートのコメントを見ると、嫌な勉強を無理やり頑張って合格したのではなく、
「小さい頃から勉強が好きで楽しくてしょうがなかった」
「分からなかったことが分かるようになり、知らなかったことを知るのが嬉しいので、自然と何時間でも勉強できた」
そんな意見がたくさんありました。
そうなるために親ができることは、
- 子供が好きなことを否定しない
- 夢中になって取り組むことを邪魔しない
- 考えることが楽しいと思える環境を与える
ということ。
また、
- 子供の自発的な発想の中で、自由にたくさん遊ばせる
ことも大事なようです。
そしてやはり一番大切なのは、子供への愛情。
東大に入る子の家庭は、家族の仲が良く会話が多いこともわかっています。
心を込めた読み聞かせや、親子の豊富な会話の中で、子供の脳はグングン育っていくんですね。
実際に東大に入るための勉強をするのは中学や高校に入ってからだけれど、子供の頭や心の素地が作られるのはまさに幼児期。
たっぷりの愛情と刺激で、子供の能力をのびのびと育てていきましょう!
★こちらの記事も読まれています 『思考力』という言葉をよく耳にするようになりましたよね。 小さいお子さんがいらっしゃる親御さんは、 「幼児期から思考力をつけるべき?」 「どの幼児教材も『思考力を養う』と書いてあるけれど、どれがいいの ... 続きを見る
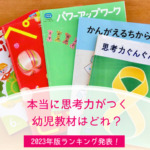
思考力が本当につく幼児通信教材ランキング【2024年】
こちらの記事も読まれています
子供が年少さん(3歳)になると、 「何か通信教育を始めようかな?」 「でも、まだお勉強を始めるには早過ぎるのかな…?」 と迷う方も多いと思います。 ここでは、モンテッソーリ教育とチャイルドコーチングの ... 近年注目を集めている『モンテッソーリ教育』。 将棋の藤井聡太さんが幼少期に受けていたことで、気になっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか? でも、 「いろいろな調べると難しそうだし、教具などが必 ... 幼稚園や保育園の年中・年長さんくらいになると、何かしらの学習ドリルや幼児教育教材を始めるご家庭が増えてきますよね。 と悩む方も多いと思います。 モンテッソーリ教育とチャイルドコーチングの指導者で1児の ... 早生まれは勉強も運動も不利? でも優秀な実績を上げているのは早生まれ! 早生まれのお子さんを持つ親御さん、いろいろと心配が尽きませんよね。 月による出生数の偏りはあまりないので、単純に計算すると、同学 ... 『小1の壁』と言うと、共働き家庭の社会的な問題を指すのが一般的。 至れり尽くせりの保育園とは違い、早い下校時間、平日の行事、長期休暇など、働くママさんには頭の痛い問題です。 でも待ってください!親だけ ... PR:Z会 難関校の合格実績で有名な『Z会』が開講した幼児コース。 息子が1年半受講してどうだったか? モンテッソーリ教育とチャイルドコーチングの指導者で、1児の母でもある筆者が、実際に受講して感じた ... PR:Z会 Z会幼児コースを検討している方で、 「Z会の実体験学習『ぺあぜっと』って一体何をするの?道具は?効果はある?」 と気になっていらっしゃる方もいるかと思います。 はっきり言って、このZ会幼児 ... 子供が生まれてしばらくすると、だんだんと『幼児教育』というものが気になってきますよね。 「なにか幼児教育を受けさせたほうがいいのかな?」 「そもそも幼児教育って必要なの?」 と悩む方も多いかと思います ... PR:ポピー 幼児向けの通信教育教材は年少さん(3歳)から始まるものが多いけれど、 「3歳までの知育ってどうしたらいいの?」 「何もしないで大丈夫かな…?」 と不安になる親御さんも多いのではないでしょ ... 「小学校に入る前から英語の学習を始めたほうがいいの?それともまだ早過ぎる?」 と迷っていらっしゃる親御さん、多いのではないでしょうか? ネットで検索しても、 「幼児のうちから、英語の音に慣れておいたほ ...

3歳(年少)におすすめの通信教育は?学習の効果と弊害も要チェック!

モンテッソーリ教育とは?大切なのは親の接し方

幼児期の子供は一日どれくらい勉強すればいいの?

早生まれが不利にならない育て方・劣等感を払拭しよう

小1の壁は子供にもある!叱り過ぎは危険!? 入学後の注意点
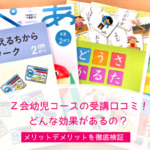
Z会幼児コースの口コミ!面倒?難しい?でもあと伸び効果は期待大!
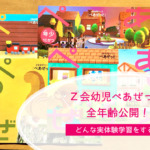
Z会幼児ぺあぜっとの実体験学習で何をするの?全年齢内容口コミ

幼児教育とは?早期教育とどう違う?
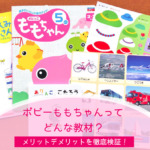
幼児ポピー2歳向けももちゃんの口コミ感想・ピカイチの情操教育教材
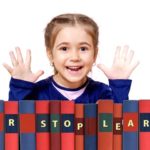
幼児の英語教育は必要? 弊害があるって本当?




